子供が親の借金を返済する義務があるのか?~相続した場合はどうなる?~
2025/02/07

■子供は親の借金の返済義務を負うか?【ケース(a)】
■親が子供の借金の返済義務を負うのか?【ケース(b)】
■保証人であっても勝手にさせられた場合は責任を負わない
■まとめ
■相続が発生した場合は、子供でも親の借金を返済する義務を負うことがある
① 相続とは何か?
② 相続放棄による方法
③ 限定承認による方法
■借金問題の無料相談・診断
・【 おすすめ法律・法務事務所ランキング 】
![]()
■ ケース(b)「突然に、勤務先に貸金業者が現れ、返済が滞っている息子の借金を親の私に返済しろと迫ってきた、どうしたらいいのか?」
■ 親が借金を作った原因は色々ある
親が自らの事業に失敗してつくった借金を返済しないまま雲隠れしたとか、親がギャンブル狂で、借金を積み重ねそのまま行方不明になったとか、
あるいは、友人の借金の連帯保証人になってしまい、その友人が借金を返済しないまま姿を消してしまって、その借金すべてが一辺に親にかかってきたとか、親が借金をつくってしまう原因はいろいろあります。
でも、往々にして、親というのは子供に心配をかけさせたくないと思うのが普通で、子供にはそんな借金を抱えているとか、そんな借金を抱えてしまうかもしれない恐れがあるとか、そういったことは話さないものです。
特にギャンブル絡みの借金はとてもとても言えたもんじゃないでしょう。でも日頃の生活態度で薄々わかってしまうことはあります。
そして、ある日突然、親あてに取り立ての電話が何本もかかってくるのです。自宅の郵便ポストに親あての督促状が頻繁に届くようになるのです。そして、貸金業者が取り立てのために住まいに直接やってくるのです。
「父親は、今行方知れずでどこにいるかわからない」といっても、しつこく取り立てにくるのです。
やがて「親が払えないなら、あんたは息子なんだから親の借金をあんたが代わりに払ってくれ」と迫られ、挙句の果てには、冒頭(a)に述べたように、自宅ではなく、突然に息子の勤務先にまで押しかけてきて・・・、息子が抱く「勤務先には迷惑をかけられない・・・」という情を利用して、取り立てを仕掛けてくることもあるかもしれません。
さて、息子に親の借金を返済する義務はあるのでしょうか? (ヤミ金でないことが前提)
その本題に入る前に、まず返済を求めるために息子の勤務先を訪れること、それ自体が違法だということは知っておいてください。
■ 子供は親の借金の返済義務を負うか?【ケース(a)】
さて、本題に戻ります。
貸金業者側は「あんたは息子なんだから・・・」という一見もっともらしい理屈を述べて返済を迫ってきますが、決してそれを鵜呑みにしてはいけません。
ただ単に、息子だという理由だけで息子が親の借金を肩代わりして支払う義務があるなんてことはないです。そんなことは毛頭ありえません。
借金の返済義務を負うのは、あくまで借金をした張本人の親です。またはその保証人(普通は連帯保証人)となった人だけです。
その親がもの凄い借金を抱えていて、客観的にみて絶対に返済する能力も資力もないと判断されても返済義務を負うのは親だけです。
子供は返済義務を負いません。
だから、子供はそんな請求に対して「頑として!」強気の態度で断っても何ら問題はありません。
ただ、もし子供がその借金の保証人になっていた場合は、返済義務を負うことになってしまいますので注意を要します。

■ 親が子供の借金の返済義務を負うのか?【ケース(b)】
以上述べたことは、冒頭のケース(b)の場合でも理屈は同じです。
実際に、借金をしているのは子供なので、借金の返済義務を負うのは子供であり、いくら子供の親であっても法的には返済義務はまったくありません。
ただ、先に述べたように親が子供の借金の保証人になっていた場合は、親は法的に返済義務を負うことになります。
■ 保証人であっても勝手にさせられた場合は責任を負わない
ところで、この保証人のケースで、往々にして(貸金業者のいわれるままに)、子供が、契約の際に保証人の欄に勝手に親の名前を記入するケースがあります。捺印も自分のモノを使います。
また、反対に、親が借金する場合に、契約の際に保証人の欄に勝手に子供の名前を記入するケースもあります。
冒頭の(a)(b)は、そのような保証人欄に子供、親の名前が書かれてあって捺印もされているからこそ、それぞれの勤務先に取り立てに現れたのかもしれませんが、先に述べたように、住居以外の場所(会社)に訪問したり、電話を掛けたり、FAXなどを送ること自体が違法です。
ただ、そういうことを抜きに考えても、保証人欄に記載された者、その当の本人が保証人になることに何ら関与も承諾もしていなく勝手にやられたものであれば、各々は保証人としての責任を負うことは一切ありません。
そんなことで保証人の責めを負われたらたまったもんじゃありませんからね。
でも、現実問題は、そう生易しいことではありません。
法律的にそうだとしても、現実もそうなるかというと必ずしもそうなるとは限らないのです。
それについては、下記の記事を参照してしてください。
■ まとめ
以上のことから、冒頭の(a)(b)の二つのケースとも「(a)は子供、(b)は親」には借金の返済義務はないということです。
だから、冒頭の二つのケースの「どうしたらいいのか、」については、ただ毅然とした態度で拒否すればいいわけです。
ただ、親子間には親子であるがゆえに特別な情があるものです。親と子、一方がもう一方のことを心配して、何と助けてあげたいという気持ちになるのは当然のことです。
だから、子は親のために、親は子のために進んで借金の肩代わりをしようと思って、返済を申し出ることがあります。
これまで述べたことは、返済する法的義務がないということでした。でも、子や親が進んで返済することを何ら妨げるものではないのです。
とは言っても、金額の大きさのこともあるので、そう簡単に肩代わりできるとはいえないでしょう。
その場合は、借金の額を減らしたり、あるいは借金をゼロにできたりする「債務整理」という確立された方法があることを伝えてあげましょう。
肩代わりするよりも、むしろこっちの方がいいです。借金をしてしまった本人の意識を変える(借金ぐせを治す)ためのキッカケにしてもらえるからです。
そして、それを試してみるために、その知識・経験をもつ専門家に相談するように勧めてみるのがいいです。
■ 相続が発生した場合は、子供でも親の借金を返済する義務を負うことがある

さて、ここまで、親がつくった借金の返済義務は子供にはないと述べてきました。
ところが、もし、親が借金を抱えたまま亡くなってしまった場合、つまり子供に相続が発生した場合は、ちょっと違った展開となります。
① 相続とは何か?
「相続」とは、一般的に、亡くなった人の遺産を相続人であるその配偶者や子供らが受け継ぐことをいいます。
「相続」というのは、普通は親の財産・資産を受け継ぐということで、プラス面を強調しがちですが、相続は親の一切合財の財産に関する権利義務を受け継ぐということですので、親に借金があれば、借金も相続の対象となります。
だから、子供が親の借金の保証人などになっていなくても、相続すれば当然にその借金は子供の借金として受け継がれていくのです。
そうなると、貸金業者は子供に対して、借金の返済請求をしてくるし、それは今まで述べたこととは違って適法な行為となるのです。
では、それを防ぐ手立てはないのでしょうか?
② 相続放棄による方法
あります。それは「相続放棄」をすることです。
「相続放棄」とは、プラスの財産のみならずマイナスの借金も含めたすべてを受け継ぐという「相続」を放棄することですから、当然にマイナス面の借金は相続されないことになります。したがって、貸金業者からの返済請求はできなくなります。
だから、親が持っていた財産よりも親が抱えていた借金のほうが多い場合は「相続放棄」したほうがいいということになります。
ただ、注意すべきことは「相続放棄」の手続きは、親が亡くなり相続することを知ってから3ヶ月以内にする必要があって、もし何もせず3ヶ月経過してしまうと、借金も含めて一切合財を相続したことになります(単純承認といいます)。
そうなると、さっき述べたように貸金業者への借金返済義務を負うことになるのです。
例えば、単純な例ですが、例えば親の財産・資産が5000万円相当あって、借金が1000万円あることがすでに確定されている場合は、まずは5000万円相当の財産・資産すべてを相続して、貸金業者からの借金1000万円はその中から返済するとした方が得ということになります。
ただ、実際のところは、親が亡くなって相続が発生した段階では、親は実際にどのくらいの財産・資産をもっていたのか? 反対にどのくらいの借金・負債を抱えていたのか?すぐには判断しにくく、その判明には時間がかかる場合があり得ます。
当初は、あきらかにプラスの財産・資産が多いと思っていても、後からとんでもない額の借金・負債があることが判明して、プラスの財産・資産とマイナスの財産(借金)を計算すると、明らかにマイナスの借金の方が多いことが分かってしまうことだって往々にしてあるのです。
そうでありながら、先に述べたように「相続放棄」するという判断は相続があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。
要は「相続(単純承認)」するか「相続放棄」するかを判断する期間が非常に短いです。ぐずぐずしているとあっという間に来てしまいます。そして、そのまま過ぎてしまうと自然と「単純承認」となって、借金含めて全てを相続することになってしまうのです。
③ 限定承認による方法
それに対処する方法として「限定承認」というやり方があります。
「限定承認」とは親がプラスの財産とマイナスの借金の両方を残していた場合、子供はプラスの分だけを引き継ぎ、借金の部分はプラスの財産・資産を超えない範囲で相続するということです。
どういうことかというと、
「単純承認」とは、プラス面の財産、マイナス面の借金を問わずすべてを受け継ぐこと。「相続放棄」とは、プラス面の財産、マイナス面の借金を問わずすべてを受け継がない、放棄するということです。
そして「限定承認」とは、イメージとしては「単純承認」と「相続放棄」の中間的存在です。
例えば、
後からプラス面の財産が2000万円、マイナス面の借金が1300万円と判明した場合は、2000万円から1300万円を引いた700万円を相続します。
後からプラス面の財産が2000万円、マイナス面の借金が2300万円と判明した場合は、プラス面の財産2000万円を相続し、マイナス面の借金はプラス面の財産2000万円を限度として相続して、両者をもって借金をチャラにします。そして、残りの借金300万円は相続を放棄するやり方です。
こうすることによって、相続財産の調査で、後からプラス面の財産の方が多いと判明したら、そのまま問題なく受け継ぎますが、もしマイナス面の借金の方が多いと判明した場合は、プラス面の財産を限度でしか、マイナス面の借金を相続しないという機会を確保できるので、そういった面では「限定承認」は非常に便利な制度といえます。
いずれにしても、相続の手続き、相続放棄の手続きは専門的であり、ましてや限定承認は利点があるものの、その手続きは複雑で面倒くささが顕著です。
だから、その辺の知識に長けた専門家に依頼する必要があります。
■ 借金問題・無料法律相談のご案内
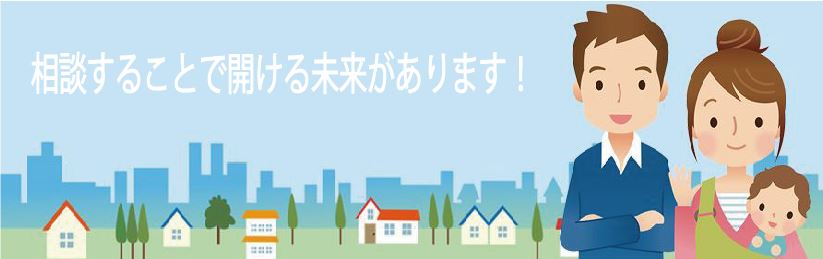
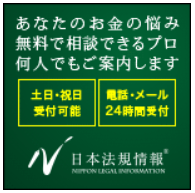 日本法規情報-債務整理相談サポート-
日本法規情報-債務整理相談サポート-● 申込みはオンラインで24時間365日可能。複数の事務所を案内
● 登録された全国の法律事務所の中からあなたに合った事務所を案内
● 相談相手の専門家をなかなか決められない人には欠かせないツール
もう少し具体的に言うと、借金問題といってもその有り様は千差万別です。当然に解決へのプロセス及び解決の方法も異なってきます。そういったなか、専門家であっても分野によっては得手不得手があります。だから、この制度は依頼人の希望に十分に応えるために、それに適した専門家を選んで専門家と依頼人を結ぶつけるサービスを行っているのです。そして、一件の依頼につき複数の法律事務所をご案内します。

したがって、初めての方がなんのツテもなく依頼人の希望に沿った事務所を探すのは結構大変なことだし、さらにまだまだ一般人にとっては弁護士事務所の敷居はまだまだ高くて最初から弁護士と相対することになると、緊張して自らの借金問題について正確に伝えられない恐れもあります。だからこそ、依頼人と専門家との間の橋渡しの役割を果たす「日本法規情報」のような存在が重宝されるのです。そして、現在では毎月3000人もの相談者がこの無料相談ツールを利用しています。
「債務整理相談サポート」の申し込みは、オンライン上で24時間どこにいても1分程度で必要項目を入力ができ申し込みが完了します。その後にその入力内容に沿った複数の事務所が案内されます。その手順は基本的には下記の(1)~(6)の順で進みます。依頼人が各々事務所に出向きそれぞれの専門家と面談して、事務所によって濃淡はありますが、依頼人にとって関心事である「あなたに合った借金を減らす方法はあるのか?それは何か?」と「おおよそどのくらい借金が減額されるのか?あるいは全額免責可能なのか?」「どうやってリスクを回避するか?」等々が回答されるので(ここまでが無料)、後はどの法律事務所にそれを実現するための債務整理手続きを依頼するかを依頼人自身が判断して決めることになります。
![]()
(1)電話またはオンライン上のお問い合わせフォームに必要項目に入力して申込する。
(2)相談パートナーより申込日より3営業日以内に電話またはメールにて相談内容の確認と専門家の希望条件をお尋ねします。。
(3)依頼人の要望する条件に合った事務所を複数案内します(平均3~5事務所)。
(4)電話かメールで案内された事務所とやり取りして無料相談の日程を調整する。
(5)依頼人の方から直接事務所に出向いて無料相談を受ける(案内されたすべての法律事務所と無料相談可能)。
(6)無料相談を受けた複数の法律事務所の中から実際に債務整理手続きをお願いする事務所を決めたらをその事務所に依頼する。なお、必ずしも具体的な債務整理手続きを依頼することなく無料相談で終わってもかまいかせん。